こんばんは。Toruです。
今回はHDD内のwindows OSやデータのクローンを作成し、新しく増設したM.2 SSDに丸ごと入れていきたいと思います。
なぜこんなことをするのかというと、こうすることでbootが爆速になり、起動する時間がかなり短縮されます。かなり。自分がやってみた軌跡として書きます。
■イメージ画像
それではいきましょう!
M.2 SSDの説明と使用するM.2の紹介
M.2 SSDというのはこの様なものです。

名前についている「M.2」というのは接続規格の一種です。接続の規格にはSATA、mSATAとM.2があります。
詳しいことは省略しますが、通信速度は
SATA<mSATA<M.2 SSD
の順になり、M.2は40Gbps(4,000MB/s)という爆速さで通信することができます。
これはSATA接続時の約7倍の通信速度になります。
取り付け方法がマザーボードのM.2端子に直接接続するタイプなのでサイズも小さくする必要があります。
そのためM.2 SSDのサイズは以下の様にそれぞれ決まっています。
またM.2のタイプには3種類あります。
使用するマザーボードによって対応するタイプが異なるので、M.2を使用する際はマザーボードがそのM.2のタイプに対応していのか調べる必要があります。
- M.2 SSDの「M.2」とは接続規格の一種。
- 通信速度は40Gbpsで、SATA接続時の約7倍の速度。
- マザーボードに直接差し込む(接続する)のでサイズは小さく、マザーボードの種類によっては対応するタイプが異なる。
- 参考サイト1:https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_parts_m2
- 参考サイト2:https://pasoju.com/ssd-difference/
そして今回使用するM.2 SSDは「CORSAIR」製のFORCE SERIES MP510(NVMe PCle Gen3 ×4)です。
今回、私が買ったのは480GBのもので、Amazonで12,000円くらいで買いました。
さらに、960GBでも25,000円で買えでしまいます。ほんとSSDって最近安くなっていますよね。
そして、今回使用するM.2 SSDにはヒートシンクをつけます。
なぜヒートシンクをつけるのかというと、実はM.2 SSDはとても発熱がすごいです。
かなり負荷をかけると80℃を普通に超えていき、最悪の場合システムが処理速度が遅くなったり停止する場合があります。
このヒートシンクがいい!というのはないのですが、PC内は無駄がないように設計されているのでなるべく薄型のヒートシンクを選ぶようにしましょう。
ヒートシンクをつけたM.2 SSDを取り付ける
それではヒートシンクをつけたM.2 SSDをマザーボードに接続します。
ヒートシンクのつけ方はめちゃくちゃ簡単で付属の両面テープをM.2に貼り付けてそれにヒートシンクを取り付けるだけです。
・上がヒートシンク用の両面テープで、下がM.2 SSD。物にもよるがヒートシンク用の両面テープは2枚あり、それぞれ厚さが違う場合がある。
・両面テープをつけてヒートシンクの下の部分のつけた画像。見えづらいけど。この後上にヒートシンクをつけねじ止めすれば終わり。
・M.2はここに差し込みます。マザーボードに書いてあるので探すのは簡単でした。今回使用するタイプはM.2 type2280なので写真でいう一番右のところにねじ止めします。ネジは大体ヒートシンクの予備用のネジで大丈夫です。
・これが取り付けた後の写真です。写真では結構厚さがあるように見えますがグラボに干渉することなく取り付けることができました。
HDD内のクローンを作成&M.2に入れる
では早速クローンを作成していきますが、その前にM.2 SSD装着前と後で起動時間や処理速度を比較したいので、ここで今の処理速度を計測しましょう。
今回使う処理速度計測ソフトはCrystal DiskMarkというフリーソフトを使用します。「速度計測といえばこのソフト!」と言えるぐらいメジャーなソフトです。
Crystal DiskMarkをダウンロードする→https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/
Crystal DiskMarkの使い方→https://pc-karuma.net/windows-crystaldiskmark-hdd-ssd-speed-test/
現状の処理速度を表しています。
めっっっっちゃザックリ説明すると、上二つが順番に情報を書き込み読み込みのときのスピードで、下二つはランダムに情報を書き込み読み込みの時のスピードです。
Q8T1は8個のキュー(待ちのこと?)1スレッドという意味です。まあ大体は上の方を見れば大丈夫だと思います。ってか、遅っ!
では早速HDD内のクローンを作っていきます。
今回クローンを作成するのに使うツールはEaseUS ToDo Backupを使っていきます。
(※注意:クローンを作成するときは必ずバックアップを取っておきましょう。筆者はバックアップを取っていなかったのですがこの後痛い目を見ることになります…。)
EaseUS ToDo Backupをダウンロードする→https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
EaseUS ToDo Backup公式ページ→https://jp.easeus.com/backup-software/free.html
EaseUS ToDo Backupの使い方→https://tarelife.com/clone-ssd/
上の画面はクローンが作成し終えたときの画面です。
クローン作成自体は1時間ぐらいかかりました。
最初の画面でクローンの保存先はM.2 SSDに設定するので、終了画面が出ても特に操作する必要はありません。めちゃくちゃ便利ですね。
これでもうクローン作成は終了。
これでもうOS起動が爆速になっているわけです。
それでは試しにCrystal DiskMarkで速度を計測してみましょう。
これがM.2にWindows OSを入れた後の処理スピードを計測した物です。
...素晴らしい!!!早すぎる!!!ありがとうM.2!!!
M.2変更前と比べて断然早くなったのが分かります。
これでWindowsの起動速度も速くなるはずです!早速測定してみましょう!!!
そして事件が起こった
windowsを再起動してみるとこんな画面が出てきた。
えっ?自動修復?初めてみましたよこんなの。意味がわからない。最初はwidnowsが壊れてしまったのかと思いました。焦りましたね。爆速になって歓喜の喜びからのこれですからね。ボーナスの入った袋を落としたときと同じ気持ちになりました。(そんな経験ありませんが。)
調べてみるとどうやらM.2がOSを起動するドライブとして認識されていないみたいです。
ならばBIOS画面から設定すれば解決するじゃん!…と思ったがそう上手くいかず。
ここのメニュー画面からも認識されていない。他にもいろいろ設定をいじってみたが改善されず…。
そしていろいろ試した結果、ようやく解決策を見つけました。
PCの起動時に「F12」 を連打して出てきたメニュー画面からM.2を選択するとwindowsが立ち上がりました。
ここでは認識されているのになんでBIOSメニューでは認識されないんでしょうね。
ほんと不思議です。でもまあこれも学びと捉えればいい経験だったのではないでしょうか。
そしてこの方法で起動した場合、起動時間は25秒でしたwwwファァァァァァァァァァwww
【2020/6/23追記】この問題の解決方法を記事にしました。
このBootできない問題ですが、Boot Menuから設定することで解決することができました。結構やり方が複雑なので初心者の方でもわかるように記事を書きました。
興味がある方はぜひご覧ください。
まとめ
少し後味の悪い終わり方ですが、まあこの方法ならばOSをいつも通り、立ち上げられるの良しとしましょう。
しかしOSの起動時間、データの書き込み速度などは大幅に速くすることができました。
この作業自体は大体2時間程度で全て終わらすことができましたので、誰でも比較的簡単に出来ると思います。
デスクトップPCを使っているが起動速度が遅い方はこの方法を試してみてはいかがでしょうか。
また、今回謎で終わったBoot MenuでM.2が認識されない問題ですが、いまだに解決策は見つかっていません。
今後も解決策を見つけていきますので、その時はまた記事を書きますね。もし解決方法を知っている方がいましたら教えてください。(;_;)



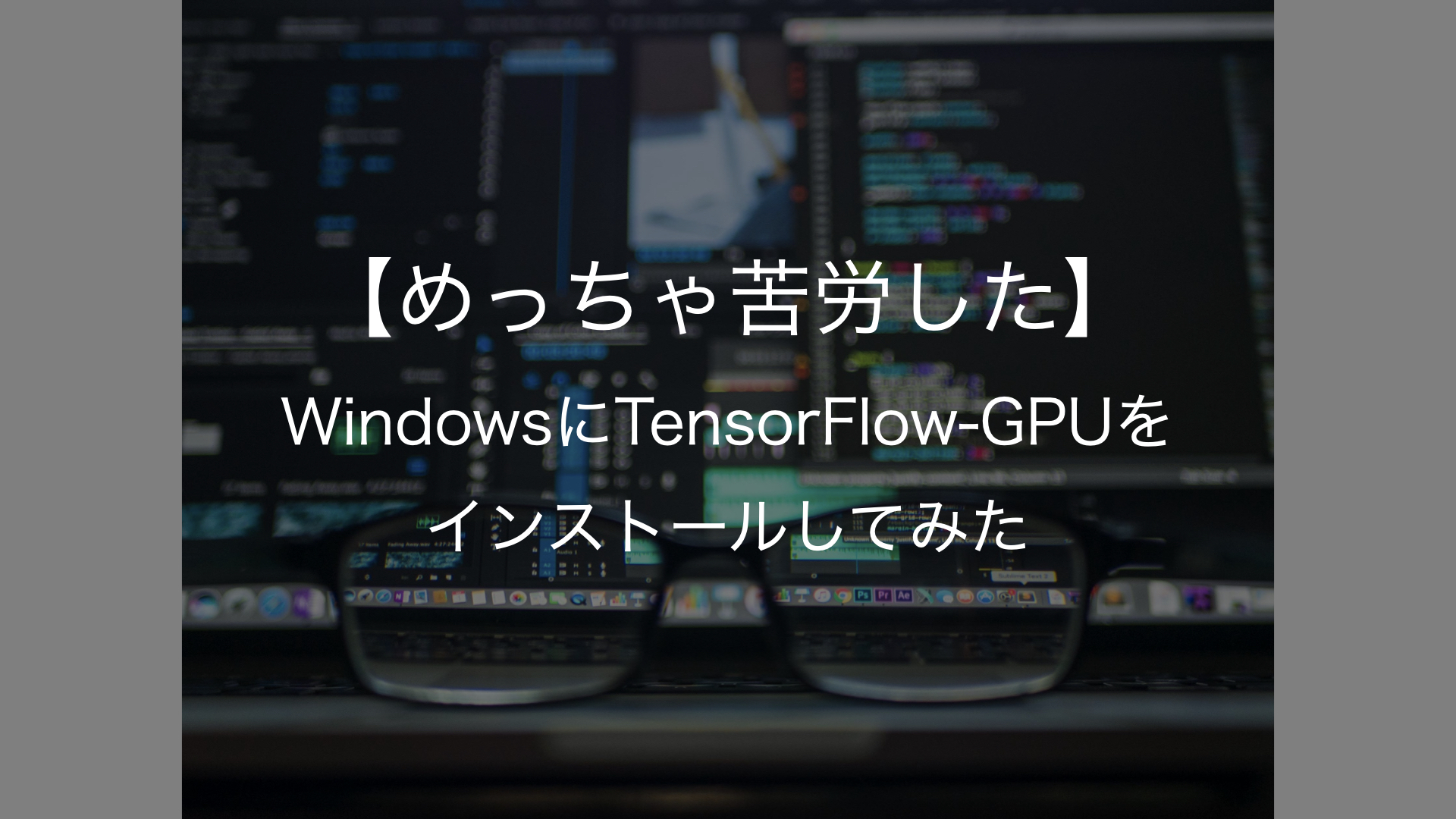








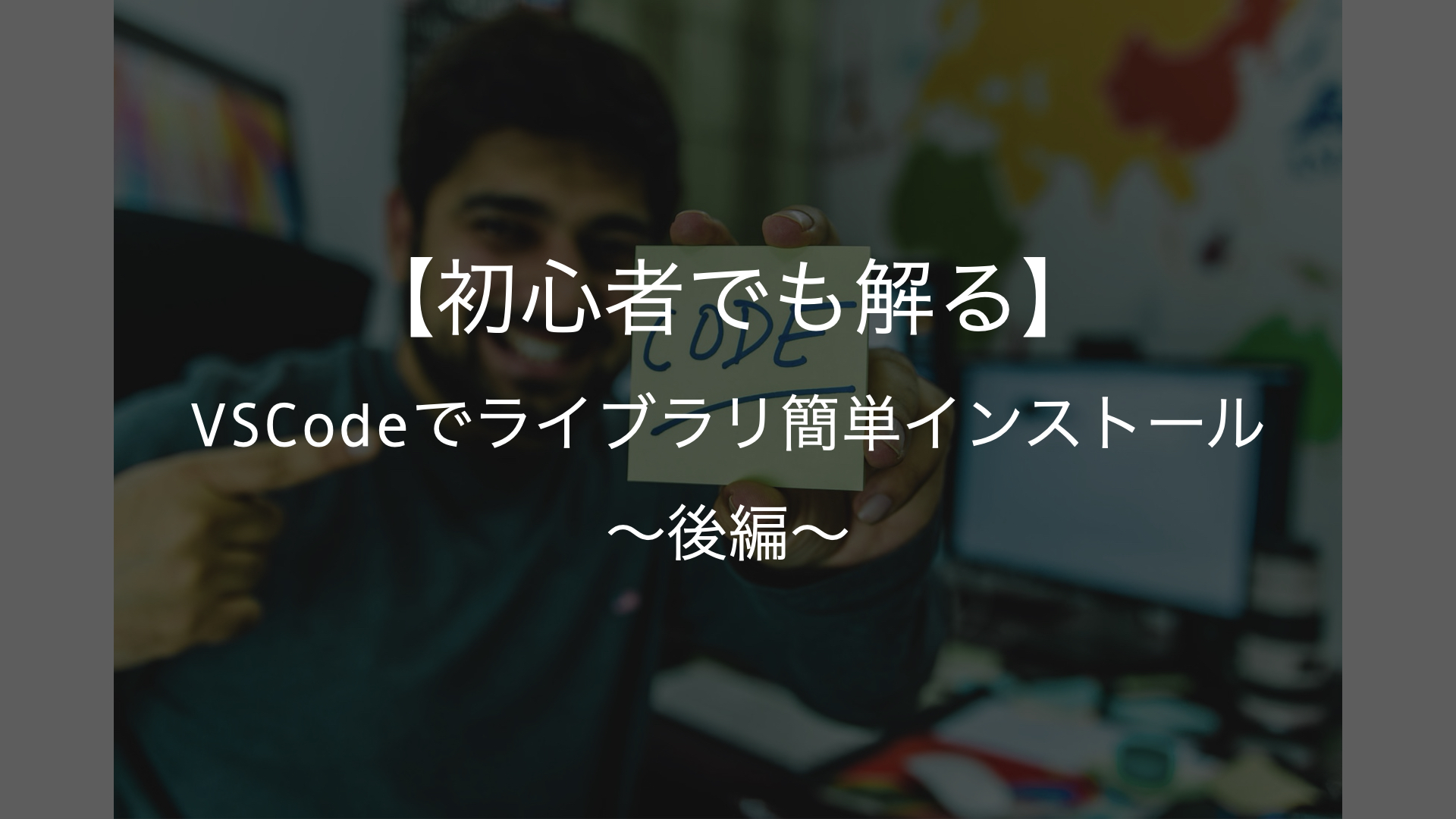



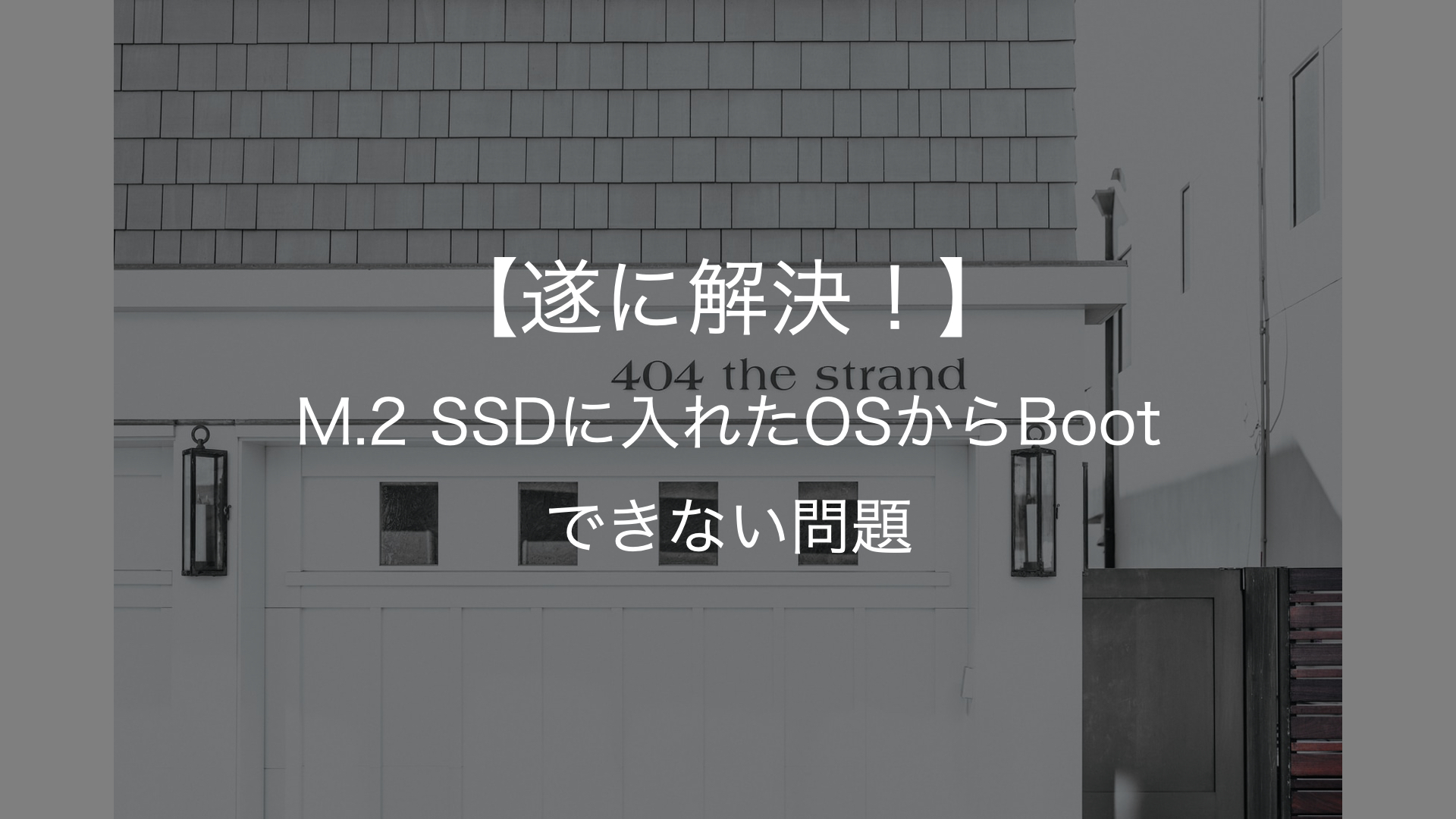

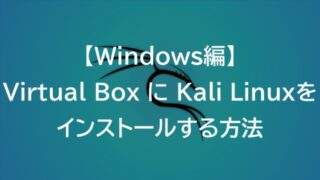























初めまして、型が古いMP500を使っていて、新しいこちらは発熱が少なくなっているかな?と思ったら、そんなことは全然ないようですね・・・
SATA<mSATA<M.2 SSD
この式は正しくありません。
SATA≦mSATA≦M.2 SSD
としましょう。
mSATAはSATA3の時代に策定されたものですから、当然mSATAが転送速度でSATAに負けることはありません。が、SATA3とmSATAは互角で、mSATAのSSD本体がコンパクトになっているだけです。
また、M.2にはSATA3とNVMeの2種類があります。当然M.2 SATA3はmSATAと同等のパフォーマンスです。しかし、MP510のようにNVMeの場合はSATAが目ではないほど速いですよね~!
それから、NVMeのSSDを選ぼうとして、単にM.2で検索すると、M.2 SATA3 SSDがヒットして価格に惹かれて購入してしまうと、最悪使えないということになるので、ご注意ください。M.2 SATA3とM.2 NVMeの間に互換性はありません。
また、5年以上が経過しているマザーボードの場合、そもそもBoot対応していないためM.2から起動できない可能性があります。
キッチリ規格策定されているのはユーザー側からもありがたいものですが、ちょっと情報が複雑ですよね・・・